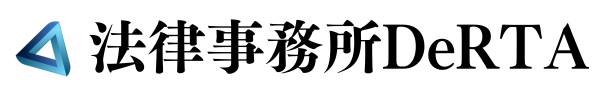【契約書のリーガルチェックが必要な理由】専門家が解説するリスク回避の重要性
ビジネスの場面で欠かせない「契約書」。この契約書は、取引先との信頼関係を形にすると同時に、将来的なトラブルを回避するために非常に重要な役割を果たします。しかし、契約書の内容を十分にチェックしないまま締結してしまい、後から思わぬ不利益を被るケースも少なくありません。契約書は法的に強い効力を持つため、一度サインや押印を行うと、原則としてその内容に拘束されます。
本記事では、「契約書のリーガルチェック」について、トラブルを未然に防ぐための観点やチェックすべきポイント、そして専門家を活用するメリットなどをわかりやすく解説していきます。リスク回避の第一歩として、ぜひ最後までお読みください。
1 なぜ契約書のリーガルチェックが必須なのか
1-1 契約書には不利な内容が含まれている可能性がある?
契約書を締結する際は、当事者同士が納得のいく形で合意したはず…と思われるかもしれません。しかし、実際に作成された契約書の条項をよく見ると、一方当事者に著しく有利・不利な内容が盛り込まれていることも珍しくありません。たとえば、以下のようなケースが挙げられます。
- 一方の当事者に過度の損害賠償義務を課す条項が含まれている。
- 通常のビジネス慣行や法令を逸脱した不当に高額な違約金が設定されている。
- 契約解除の権利が一方当事者にしか認められていない。
こうした条項は、作成・提示する側(ドラフター)が優位な立場にある場合に起こりがちです。特に契約書のドラフトをどちらが準備するかによって、内容のバランスが偏る可能性があります。したがって、相手方から提示された契約書を「難しそうだから…」という理由だけでそのまま受け入れるのは非常にリスクが高い行為です。
1-2 契約書を読んでいなかったは通用しない?
「長い契約書をすべて読む時間がなかった」「専門的な法律用語が多く、理解しきれなかった」という事情は、締結後の法的トラブルにおいてはほとんど考慮されません。契約書は、署名・捺印や電子署名をもって両者が同意した証拠となるため、“契約書をきちんと読んでいなかった”という主張は原則として通用しないのです。
また、取引先が「問題ないからサインしてほしい」と言ってきたとしても、最終的に判断するのは契約書に署名するあなた自身です。契約締結後に不利な条項に気づいて慌てても、既に法的拘束力が生じているため、簡単には撤回できません。そうならないためにも、契約書は必ず事前にリーガルチェックを行い、内容を正確に理解してから締結することが肝要です。
1-3 裁判になった場合、契約書の内容はどのように扱われるか
万が一、契約に関する紛争が生じて裁判となった場合、契約書は最も重要な証拠として扱われます。契約書に明文化された条項は、原則としてそのまま有効とみなされるため、以下のような問題に直面する可能性があります。
- 不利な条項があっても、相手方が「この契約書に同意している」と主張すれば、不利な立場で争わざるを得ない。
- 契約書にあいまいな表現が多い場合、裁判官の解釈次第で結果が左右される。
- 契約書が存在しない場合や口頭だけの合意であった場合は、証拠不十分で相手方の主張を覆すのがさらに難しくなる。
こうしたリスクを考慮しても、契約書を締結する際のリーガルチェックは必須と言えます。契約段階で慎重にチェックし、不要なトラブルを予防することが企業や事業主にとって大切な責務となるのです。
2 契約書のリーガルチェックで必ず確認すべき主たる項目
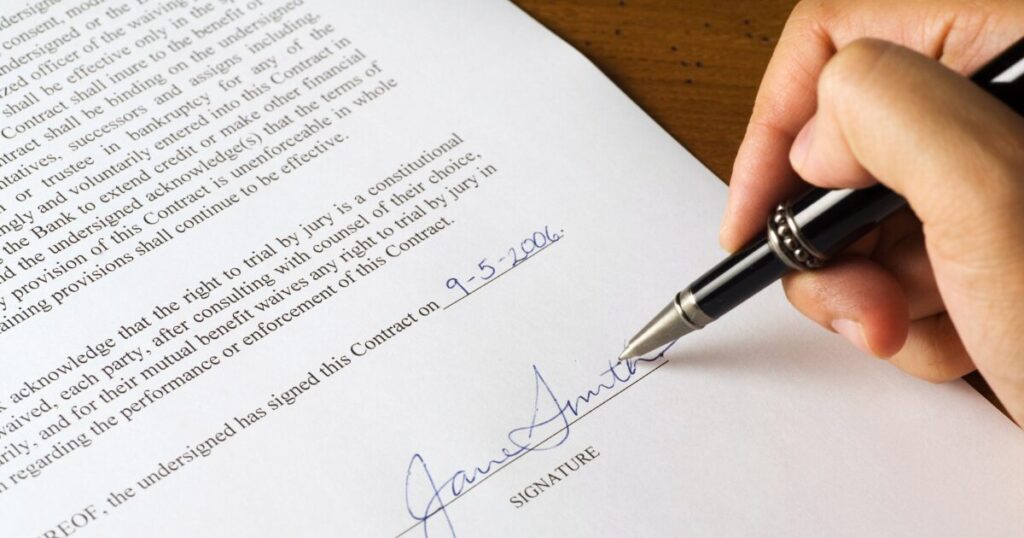
契約書のリーガルチェックを弁護士に依頼するのではなく、ご自身でされる場合でも以下の6つの事項は必ず確認するようにしてください。
2-1 契約の目的・履行内容の明確化
契約書に記載する「契約の目的」と「履行内容」は、契約そのものの本質を示す重要な部分です。例えば、モノの売買契約であれば「納品する商品や納期」「品質保証の範囲」といった具体的な事項、サービス契約であれば「業務の範囲」「成果物の仕様」「報酬と支払い条件」などが該当します。
- なぜこの契約を結ぶのか
- 具体的に何をいつまでに行うのか
- 成果物やサービスの納品基準はどう設定されているか
これらがあいまいなまま契約書を作成してしまうと、後から「こんなはずではなかった」という認識の相違が生じ、トラブルの原因になる可能性が高まります。
2-2 余事記載・記載漏れ
契約書を作成する段階では、当初の合意内容以外の事項が誤って加筆(余事記載)されている場合や、逆に本来記載すべき内容をうっかり省略してしまう(記載漏れ)場合があります。これらは契約当事者にとって、以下のようなリスクをもたらします。
- 余事記載された条項が、当事者の真意を反映しないまま有効に扱われてしまう。
- 記載漏れが原因で、あとで「重要な取り決めがまったく文書化されていなかった」ことに気づき、双方の認識がすれ違ったまま紛争へ発展する。
- 契約書内に整合性のない記載が混在し、どの条項が優先されるのか不明確になる。
余事記載や記載漏れがあった場合に「実際には口頭で異なった合意をした」は通用しません。契約書に記載されていないことは合意していないものとみなされると考えておいた方がよいでしょう。これらを発見した場合は、当事者間で早急に内容を確認し、不要な条項を削除あるいは不足条項を追加するなど、必要な修正を適切に行うことが大切です。後からの修正は手間も費用もかかりますが、将来のトラブル回避につながる重要な作業となります。
2-3 権利の帰属
共同開発や共同制作、外注(アウトソーシング)などで作成された成果物に関しては、著作権や知的財産権の帰属先を明確に定めることが不可欠です。特にクリエイティブ業界やIT業界では、開発したシステムやデザインの権利が誰に帰属するかがビジネスモデルや収益構造に大きく影響を与えます。
- 成果物の著作権や商標権は、作成者か、それとも依頼者か?
- 契約後に改変や二次利用を行う場合、追加許可や報酬は必要なのか?
この点が不明確だと、後日「権利侵害で訴えられる」「販売するはずだったのに利用を制限される」などの深刻なトラブルに発展する恐れがあります。
2-4 契約解除の可否や条件
契約の有効期間や更新方法、そして途中解約の可否は、長期契約では特に重要なポイントです。契約を締結した場合、原則としてすぐには一方的に解除できないので解除の可否や条件を記載しておく必要があります。また、相手方が契約違反をした場合にどの程度の違反で解除が可能かも明確にする必要があります。
- 契約違反や支払い遅延があった際、契約をすぐに解除できるか?
- 解約に伴う違約金やペナルティは設定されているか?
- 自動更新の仕組みがある場合、どのタイミングで解約を申し出ればよいか?
ビジネス環境が大きく変化するなかで、柔軟に対応できるよう解除条件や手続きを定めておくことで、リスクを大幅に減らせます。
2-5 損害賠償の制限・違約金条項
契約違反が起こった際に、どのように責任を追及するのかを取り決めるのが「損害賠償」「違約金」条項です。これらの条項が過度に厳しかったり、あるいはまったく規定されていなかったりするのは双方にとってリスクとなります。
- 損害賠償の範囲はどこまで含まれるか?(間接損害・逸失利益を含むかなど)
- 違約金の金額が実際のダメージに対して過大ではないか?
- 訴訟費用や弁護士費用の負担についての規定はあるか?
企業間取引においては、取引先との関係性も踏まえつつ、実情に合ったバランスの良い損害賠償・違約金条項を設ける必要があります。損害賠償の範囲が限定されているため、相手に対して損害賠償請求できない、といったことも起こり得るので必ず確認する必要があります。
2-6 裁判管轄
契約トラブルにおいては、裁判所をどこにするか(裁判管轄)が合意されているかどうかも、近年ではオンラインでの裁判が可能となったとはいえ、意外と重要です。たとえば、東京の企業が契約書上の管轄を大阪の裁判所と定めている場合、裁判が起きた際にはわざわざ遠方まで行かなければならず、時間的・費用的な負担が増大します(弁護士に依頼する場合、余計な裁判費用が発生します。)。
- 海外企業との契約では「どの国の裁判所(または仲裁機関)を利用するのか」
- 国内でも、相手先の本店所在地や支店所在地にある裁判所が指定されていないか
このような点を事前に確認し、自社にとって不利にならないよう交渉・修正することが必要です。
3 契約書リーガルチェックに専門家を活用するメリット

3-1 弁護士による顧問契約・法務のアウトソーシングの活用
契約書のリーガルチェックには、専門的な法知識と契約実務経験が欠かせません。とりわけ複雑な契約や金額の大きい取引、知的財産など専門性が高い分野においては、弁護士や法律事務所との連携が大きな安心材料となります。
- 顧問契約・法務のアウトソーシング契約を結ぶメリット:
- 継続的に法的アドバイスを受けられるため、契約書レビューのタイムラグを最小化できる。
- 紛争が発生した場合でも、顧問弁護士がすぐに対応策を講じてくれる。
- 社内法務のリソースが不足している中小企業やスタートアップにとって、外部専門家の力は大きい。
3-2 AIによる契約書チェックについて
近年は、AIツールによる契約書レビューが注目されています。AIを活用すれば、大量の契約書を効率的にチェックし、形式的な誤字脱字や定型的なリスクを素早く指摘してくれます。また、過去の判例データと照合して問題となりやすい条項を抽出してくれるなど、人的作業だけでは見逃しやすい箇所を補完してくれる点で大きなメリットがあります。
ただし、AIレビューには以下のような注意点もあります。
- あくまで機械的な抽出にとどまる場合が多く、個別事情や交渉上のバランスは考慮できない。
- 最新の法改正や判例動向をどこまで反映できているかは、ツールのアップデート頻度による。
- 社内の特有の実情や過去の経過を踏まえた対応が困難という問題がある。
したがって、やはり専門家によるリーガルチェックにより、より精度の高いリーガルチェックが必要です。
3-3 まとめ|契約書のリーガルチェックで会社を守る第一歩
契約書は、ビジネスの土台を支える極めて重要な文書です。細かい条項であっても、後になって大きな影響を及ぼす可能性があります。そのため、リーガルチェックをしっかり行い、不利な内容やリスク要因がないかを事前に把握したうえで、必要に応じて修正や交渉を行うことが不可欠です。
- 不利な条項やリスク条項を見抜き、トラブルを未然に防ぐ
- 契約内容を明確にして、当事者間の認識のズレを減らす
- 裁判リスクや損害賠償責任を最小限に抑える
これらを実現するためには、やはり専門家の力が頼りになります。企業規模や業種を問わず、契約書を締結する際には「プロのチェックを受ける」ことを検討してみてください。
3-4 リーガルチェックにお困りの方は、まずは専門家へご相談を!
法的なリスクを最小限に抑え、安心してビジネスを進めるためにも、契約書のリーガルチェックを怠らないようにしましょう。必要であれば弁護士や法務のアウトソーシングサービスを活用し、より安全かつ円滑な取引環境を整備することが、企業成長の大きな鍵となります。
法律事務所DeRTA(デルタ)では、契約書のリーガルチェックをはじめとする法律顧問・法務のアウトソーシングサービスをご用意しております。ご興味のある方は、以下のお問い合わせフォームからお気軽にお問い合わせください。